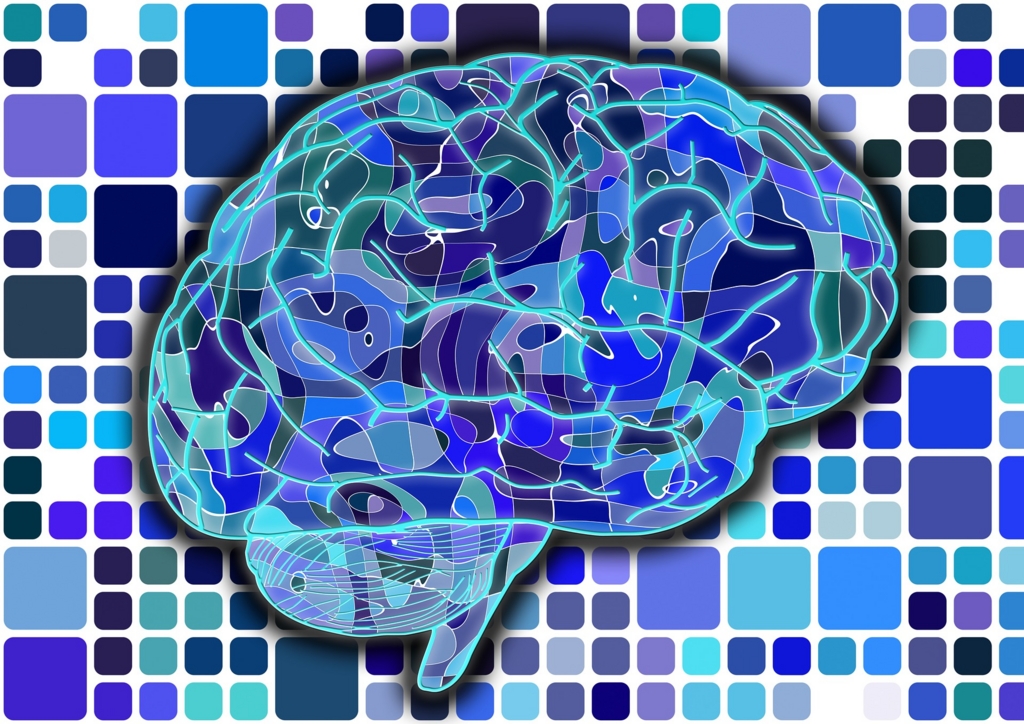
ADHDの診断と脳SPECT画像診断
脳SPECTという脳の血流を調べる検査を受けると、自分の脳の働き方の特徴がよく分かります。脳SPECTはまだ導入している病院も少なく、保険適応になっていません。脳SPECT検査の結果をしるとADHDの「できないこと」の原因がよく分かるので参考にしてください。
脳SPECT検査とは?
脳SPTCT検査は、脳の画像診断の一種です。MRIやCTでも、脳の画像をとって脳の形を見ることができます。では、MRIと脳SPECTの違いはなんでしょう?
MRIやCTは、脳の静止画像です。一方で、脳SPECTでは、脳がどのように働いているのかが分かります。つまり、脳の動画を見ることができるのです。
脳の動画といっても、実際に脳が「どくんどくん」と脈打つわけではありません。
脳は常にまんべんなく働いているわけではなく、必要に応じて必要な場所を動かしています。
脳が働いているときは、働いている場所の血流が悪くなります。
脳SPECT画像では、脳の血流を見ることができるのです。
脳SPECTでわかるADHDの脳の働き方

http://iryoukannkeisikaku.blog.fc2.com/
上の画像は脳SPECTの画像です。
青く映っている部分は血流が少なく、赤く映っているところは血流が多くなっています。
ADHDは前頭葉の血流がリラックスしている状態でも少なく、青っぽくうつります。
数学の計算問題などを解くために集中すると、前頭葉の血流は増え、通常は赤く映ります。しかし、ADHDの脳はさらに青くなります。つまり、ADHDは集中すると脳の血流が悪くなってしまうのです。
「今すぐ書類をつくらなくちゃ!」と思っても始められない。初めても集中できない。頭が回らない。
そう言った経験がありますか?それは、脳の血流が集中しなければならない状態になればなるほど悪くなってしまうからなのです。
ADHDの治療薬には、こういった脳の血流の悪さを改善する働きがあります。
脳SPECTを受けるには?
脳SPECTを受けるためには、SPECT検査を受けられる施設を探さなければいけません。
実施している施設はこのサイトから検索することができます。
なお、脳SPECT検査は保険適応にはなっていません。検査料は全額自己負担となり、大体8万円ほどかかります。
脳SPECT検査はADHDだけでなく認知症などの診断にもとても有効です。早く一般的に普及し、保険適応になるとよいですね。
↓↓ADHDの脳SPECTについて詳しく書いている本です。

「わかっているのにできない」脳〈1〉エイメン博士が教えてくれるADDの脳の仕組み
- 作者: ダニエル・G.エイメン,Daniel G. Amen,ニキリンコ
- 出版社/メーカー: 花風社
- 発売日: 2001/09
- メディア: 単行本
- 購入: 19人 クリック: 154回
- この商品を含むブログ (21件) を見る
スポンサードリンク